加齢黄斑変性とは
網膜の中心部分である直径1.5mmほどの範囲を黄斑部と呼びますが、ここが加齢によって変性することで、ものが歪んで見える(変視)、視力低下、中央が見づらいといった症状が出ます。50歳以上の方に発症することが大半で、年齢が上がるほど発症率は高くなります。なお、50歳未満の方で加齢黄斑変性に似た症状があるという場合は他の疾患による症状の可能性もあります。
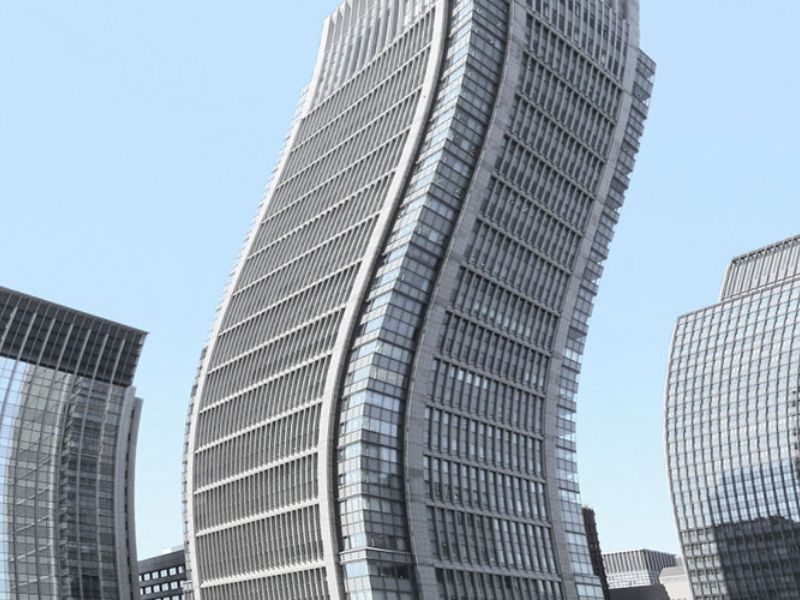
加齢によって黄斑部の細胞の働きは悪くなり、次第に酸素や栄養分の供給が低下し、老廃物が蓄積されていきます。このような状態下では異常な血管(新生血管)が生えてきやすく、異常な血管から滲出や出血を伴うので、変視や視力低下などの症状がみられるようになります。さらに進行すれば、著しく視力は低下していき、最終的に視力が0.1未満になることもあります。診断をつけるための検査では、眼底検査、OCT(光干渉断層計)、蛍光眼底造影検査があり、新生血管の状態や位置を確認します。
滲出型と萎縮型
加齢黄斑変性は滲出型と萎縮型の2つのタイプに分類されます。
加齢黄斑変性症の多くを占めているのが滲出型です。新生血管が黄斑の脈絡膜(網膜より外側にある、血管が豊富な膜)から網膜に向かって伸展することで起きます。新生血管はもろくて弱い性質のため、出血や血液中の水分の染み出しが起きやすくなります。その結果、黄斑に腫れが生じて、機能障害を受けるようになるのです。
萎縮型は、網膜の細胞と脈絡膜が老化とともに徐々に死滅していくため、黄斑の機能はゆっくりと損なわれるようになります。現時点では萎縮型の治療法は確立されておらず、進行が見られないか定期的に経過観察(眼底検査など)をしていきます。
治療について
滲出型加齢黄斑変性症では、脈絡膜新生血管をおさえることが治療となります。黄斑部の機能を維持、改善させることを目的に、抗VEGF硝子体注射を行います。当院で抗VEGF硝子体注射の治療が可能です。


